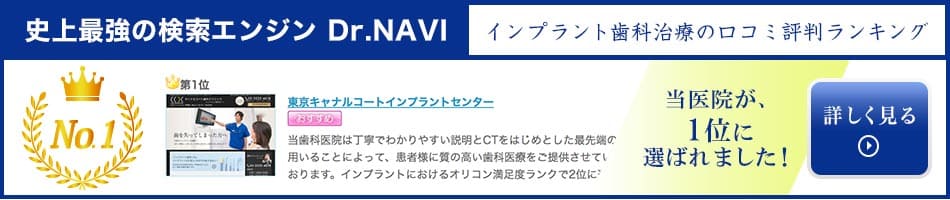診療時間 月~日・祝9:00~13:30 / 15:00~20:00
- キャナルコート歯科クリニック イオン東雲
- tel03-6221-3447
- キャナルコート歯科クリニック キャナル東雲
- tel03-3532-4618

親知らずを抜くタイミングは?
親知らず(正式名称:第三大臼歯)は、一般的に10代後半から20代前半にかけて生えてくる奥歯のことです。
上顎と下顎にそれぞれ左右1本ずつ、合計4本生える可能性があります。
しかし、現代人の顎は進化とともに小さくなっており、
親知らずが正常に生えるスペースがない場合も多くあり、
そのため、親知らずは斜めや横向きに生えてきたり、
完全に歯茎の中に埋まったままだったりと、
問題を起こしやすい歯として知られています。
では、どのようなタイミングで親知らずを抜くべきなのでしょうか?
抜歯が推奨されるケースとそうでないケース、そしてタイミングの見極め方について
詳しくお話していきます。

目次
親知らずを抜くべきタイミング
痛みや腫れがある場合(智歯周囲炎)
親知らずが中途半端に顔を出していると、
歯と歯茎の間に食べかすや細菌が入り込みやすく、
炎症を引き起こす「智歯周囲炎」を発症しやすくなります。
この状態になると、歯茎が腫れたり、ズキズキとした痛みを感じたり、
場合によっては口が開きにくくなる「開口障害」や発熱を伴うこともあります。
このような炎症が一度でも起きた場合、再発の可能性が高く、抜歯するのが一般的です。
ただし、炎症が起きている場合はすぐに抜歯することをお勧めしません。
抜歯をする際に麻酔をしますが、炎症している時は麻酔が効きづらい傾向にあります。
まずは、炎症を抗生剤を服用し治まったうえで行う場合が多いです。
虫歯や歯周病の原因になっている場合
親知らずが正常に生えていないと、歯ブラシが届きにくく、
汚れが溜まりやすくなります。
その結果、親知らずや隣の歯(第二大臼歯)が虫歯や歯周病になりやすくなります。
とくに隣の歯に悪影響が出ている場合は、早期に抜歯を検討しましょう。
親知らずが原因で隣の健康な歯を失うのは避けなければなりません。
横向きや斜めに生えている場合(埋伏歯)
親知らずが横向きに生えていて骨の中に埋まっている「水平埋伏歯」や、
斜めに生えている「傾斜歯」は、将来的にトラブルを引き起こす可能性が高い
と言われています。
これらは自然に正常な方向に動くことはほとんどなく、放置すると周囲の歯列を乱したり、
歯の根を圧迫して痛みや炎症を引き起こすこともあります。
そのため、レントゲンやCTで診断した結果、将来的なリスクが高いと判断された場合は、
症状が出ていなくても予防的に抜くことを勧めるケースがあります。
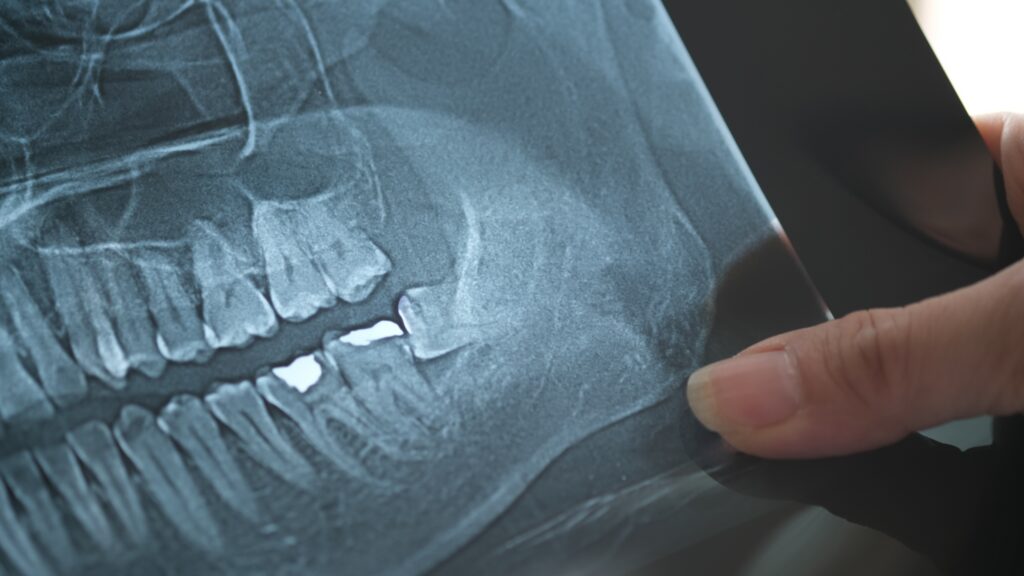
矯正治療を考えている場合
歯列矯正を予定している方にとって、親知らずの存在は歯の動きに
影響を与える可能性があります。
特に下の親知らずが横向きに埋まっている場合、
前歯を圧迫して歯列の乱れを引き起こすことがあるため、
事前に抜いておくことが勧められる場合があります。
矯正歯科の先生と相談して、必要性を評価することが大切です。
抜歯を急がなくてよいケース
以下のような場合は、必ずしもすぐに親知らずを抜く必要はありません。

まっすぐ正常に生えていて、かみ合わせに問題がない
親知らずが真っすぐに生えており、上下の歯としっかり咬み合っていて、
歯磨きがきちんとできている場合は、そのまま残しておいても問題はありません。
むしろ、将来的に他の歯を失った際の代用歯として利用できることもあります。
痛みや腫れがまったくない場合
症状が出ていない親知らずは、定期的な検診とX線撮影を通じて経過観察することも
一つの選択肢です。
とくに高齢者の場合、抜歯によるリスク(骨折や感染、治癒遅延など)も増すため、
慎重な判断が必要です。
全身疾患や服薬状況によるリスクが高い場合
心臓病、糖尿病、骨粗鬆症などの持病を持っている人や、
抗血栓薬などを服用している場合は、抜歯に伴う合併症のリスクが
高くなる可能性があります。
これらのケースでは、かかりつけの先生と歯科医師と連携を取りながら、
慎重にタイミングを決めることが求められます。
タイミングを決める上でのポイント
親知らずの処置は、一人ひとり異なるため、一般論だけで判断するのは避けた方がよいです。まずは歯科医院でレントゲン(パノラマ写真)やCTを撮ってもらい、
親知らずの位置、向き、周囲の骨や神経との関係性を確認しましょう。
そのうえで、「すぐ抜いた方がいいのか」「様子を見るべきか」を、
歯科医師と相談しながら決めることが大切です。
また、親知らずの抜歯は生え方や形状によっては、一般歯科では行わず、
設備が整った大学病院や総合病院を紹介される場合があります。
親知らずの位置が、下あごに通っている神経(下歯槽管神経)に接していたり、近い場合や
先述した全身疾患を持っている患者様などがそれにあたります。
抜歯後は腫れたり、痛みが数日続くこともあるため、仕事や学業に支障が出ないように、
予定が調整しやすい時期(例えば連休や休暇の前)に行うことをお勧めします。
抜きたくない場合に考えるべきこと
診断の結果、抜歯を推奨されたが、どうしても抜きたくない方もいらっしゃると思います。
その場合はどうすればよいのかもお話しします。
なぜ抜きたくないのか理由は?
たとえば、手術が怖い(痛み、腫れ、麻酔など)、仕事や学業に支障が出るのが不安、
過去にトラウマがある、高齢や持病があるためリスクを避けたいなど、
理由によっては、歯科医師と相談することで不安が解消される方法や代替策が見つかることもあります。
抜かないために必要な条件は?
親知らずを抜かないなら、トラブルを予防するためのセルフケアが非常に大切です。
ワンタフトブラシなどで奥歯を重点的に磨く、デンタルフロスや歯間ブラシを活用する、
マウスウォッシュで口内の細菌を抑制など徹底したケアを行いましょう。
また、3~6か月ごとの歯科検診と歯科衛生士によるプロの清掃をしてもらうことも重要です。
しかしながら、親知らずは一番奥にあり、磨きにくく汚れがたまりやすいです。
限界はありますので、抜歯をすることがお口のケアになるのであれば、
やはり抜歯を考えていただくことが賢明ではあります。
抜かずにいたことで起きうるリスク(理解しておくべき点)は?
「抜きたくない」という気持ちは至極当然ですが、放置することで起こりうる
リスクも理解しておくことが大切です。
智歯周囲炎:繰り返す腫れと痛み(とくに体調不良や疲労時に起こりやすい)
虫歯や歯周病:自分の親知らずだけでなく、隣の歯にも悪影響
歯並びの変化:特に矯正後は後戻りの原因になることも
その他:顎の骨に嚢胞や感染を起こすことがある
リスクが現れた時点で抜歯が必要になり、「もっと早く抜いておけばよかった」となる
ケースも少なくありません。
まとめ
親知らずを抜くタイミングは、
「現在トラブルが起きているか」
「将来的にリスクがあるか」
「患者さんの年齢や健康状態」など、
複数の要素を総合的に考慮して決定されます。
すでに痛みや腫れがある場合は、早めの処置が必要ですし、
症状がなくても将来的なリスクを考えて予防的に抜歯を行う場合もあります。
一方で、問題がなければ無理に抜かなくてもよいケースもあります。
大切なのは、自己判断せずに歯科医に相談し、正確な診断を受けたうえで、
最適なタイミングを見極めることです。
気になることがあれば、早めに歯科医院を受診してみましょう。
医療法人社団天白会キャナルコート歯科クリニックイオン東雲院
およびキャナルコート歯科クリニック キャナル東雲院では、
随時急患を受け入れております。
歯にお痛みなどがなくても、定期的なお口のケアやお掃除はとても重要です。
土日祝も20時まで診療しており、駐車場も完備しています。
当院であなたの歯の健康をサポートいたします!
このブログの監修者
医療法人社団天白会
キャナルコート歯科クリニック イオン東雲
院長 大倉 康平

医療法人社団天白会
理事長
キャナルコート歯科クリニック キャナル東雲
院長
歯学博士 山田健太郎 日本口腔インプラント学会 専門医


キャナルコート歯科クリニック
イオン東雲
- 東京都江東区東雲1-9-10
イオン東雲ショッピングセンター2F - tel03-6221-3447
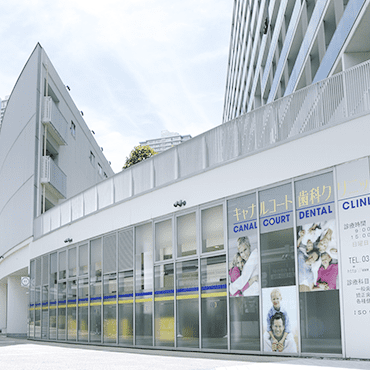
キャナルコート歯科クリニック
キャナル東雲
- 東京都江東区東雲1-9-22
ブリリアイスト東雲キャナルコート1F - tel03-3532-4618